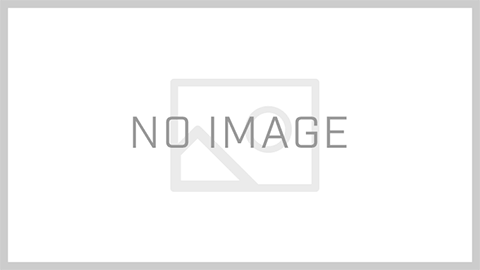目次
高額介護合算療養費制度とは
高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。
- 支給要件:医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた場合に、当該合算額から限度額を超えた額を支給。
- 限度額 :被保険者の所得・年齢に応じて設定。
- 費用負担:医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて支給額を按分して負担
年齢・所得区分ごとの合算算定基準額(自己負担限度額・年額)
後期高齢者医療制度加入者および70歳以上国民健康保険加入者
| 所得区分 | 要件 | 限度額 | ※限度額(平成30年8月から) |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (上位所得者) | 世帯に市民税課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方 | 67万円 | 現役並みⅢ ・ 212万円(課税所得690万円以上) 現役並みⅡ・ 141万円(課税所得380万円以上) 現役並みⅠ・ 67万円(課税所得145万円以上) |
| 一般 | 現役並み所得者・区分1・2.に該当しない方 | 56万円 | |
| 住民税 非課税 世帯(区分2) | 市民税非課税世帯で、区分1に該当しない方 | 31万円 | |
| 住民税 非課税 世帯(区分1) | 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方または市民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方 | 19万円 |
※70歳から74歳までの方の基準額(平成30年8月診療分から)
| 区分 | 所得要件等 | 基準額 |
| 現役並みⅢ | 課税標準額が690万円以上の世帯 | 212万円 |
| 現役並みⅡ | 課税標準額が380万円以上、690万円未満の世帯 | 141万円 |
| 現役並みⅠ | 課税標準額が145万円以上、380万円未満の世帯 | 67万円 |
| 一般 | 課税標準額が145万円未満の世帯等 | 56万円 |
| 市民税非課税世帯等 | 低所得者ΙΙ(同一世帯の世帯主及び国保の 被保険者全員が市民税非課税の場合 (低所得者Ιの方を除く)) | 31万円 |
| 市民税非課税世帯等 | 低所得者Ι(同一世帯の世帯主及び国保の 被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの 被保険者における給与、年金等の収入から 必要経費、控除額(年金については 控除額80万円)を引いたとき、各所得が いずれも0円となる場合) | 19万円 |
70歳未満の国民健康保険加入者
| 区分 | 所得要件(※) | 基準額 |
|---|---|---|
| ア | 901万円を超える世帯 | 212万円 |
| イ | 600万円を超え、901万円以下の世帯 | 141万円 |
| ウ | 210万円を超え、600万円以下の世帯 | 67万円 |
| エ | 210万円以下の世帯 | 60万円 |
| オ | 市民税非課税世帯等 | 34万円 |
同一世帯に70歳未満と70歳以上の方がおられる場合は、まず70歳以上の方の自己負担額を合算し支給額の計算をした後、そのなお残る自己負担額を70歳未満の方の自己負担額と合算して支給額を計算します。支給額の計算時にそれぞれの基準額を適用します。
計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月です。
申請方法について
支給対象者には市町村より通知を送付されますので、保険年金課へ申請してください。
- 1.介護保険者(市町村)に支給申請書兼自己負担証明書交付書を提出する
- 2.介護保険者に自己負担額証明書を交付してもらう
- 3.医療保険者(健康保険組合など)に対して自己負担額証明書の書類を添付し、支給申請書を提出
- 4.医療保険者から介護保険者に支給額の計算結果が送られる
- 5.医療保険者と介護保険者から被保険者に対して、支給決定通知書の送付と現金が支給される
※次に該当する方には申請のご案内ができない場合があります。
対象期間(7月~翌年8月)の1年間に、
- 被用者保険または国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方
- お住まいの市町村が変わった方
- 被用者保険から国民健康保険に移られた方
申請書類について
- 支給申請書(兼交付申請書)
- 医療保険の被保険者証(後期高齢者医療制度もしくは国民健康保険)
- 介護保険の被保険者証
- マイナンバーの記入と提示
スポンサーリンク